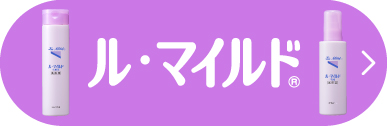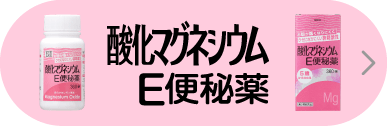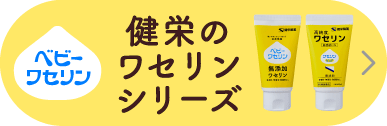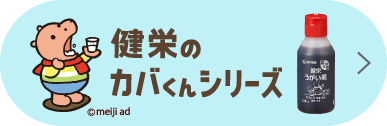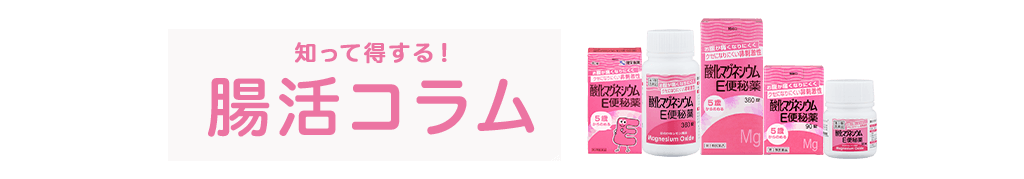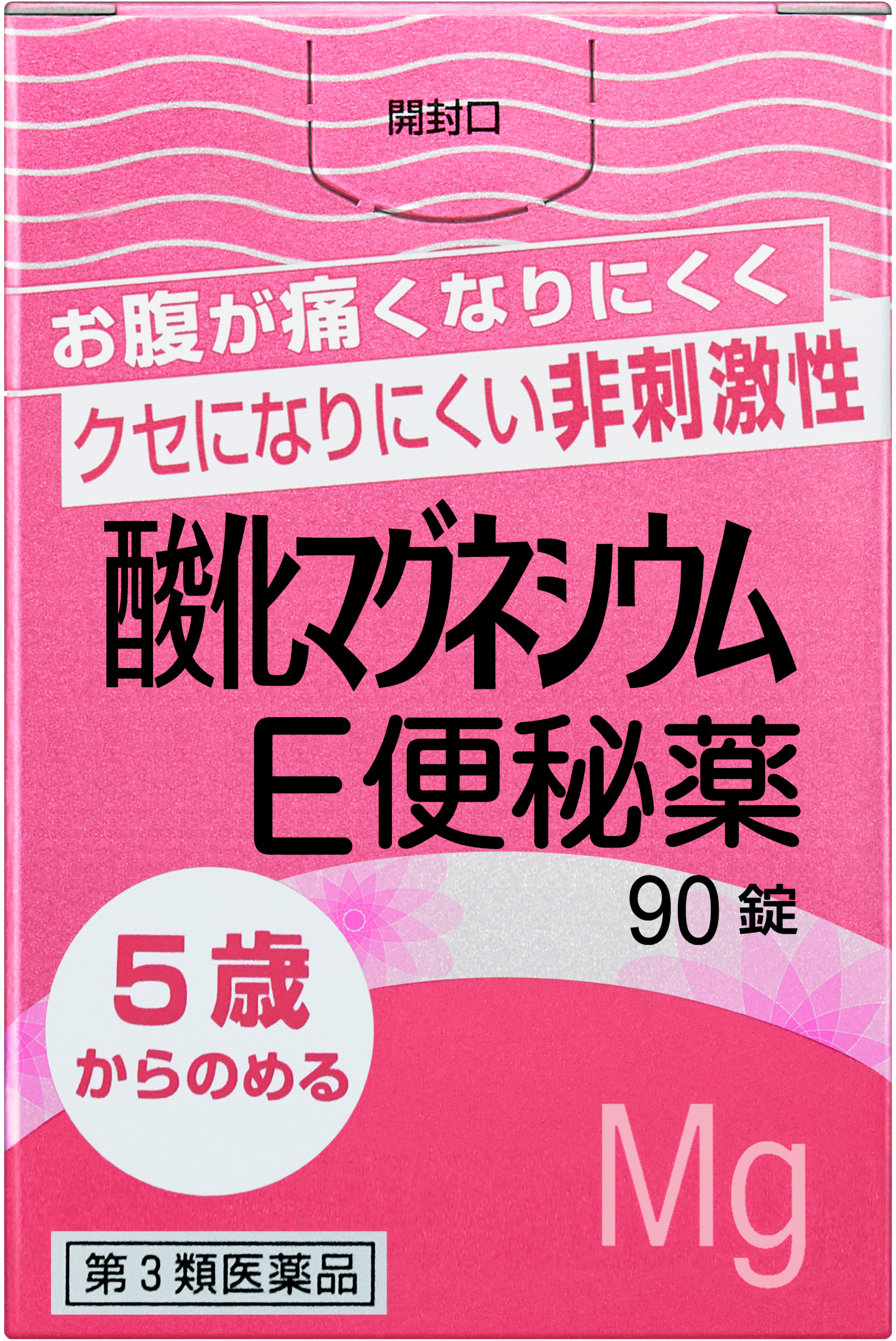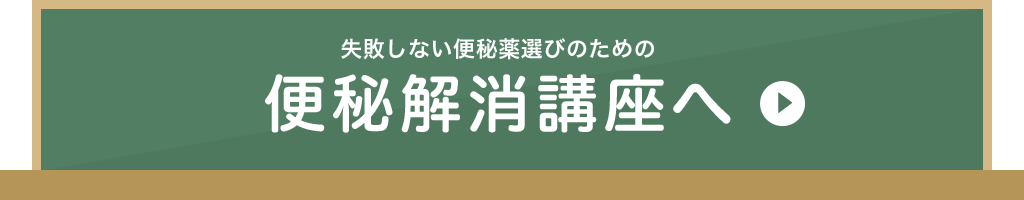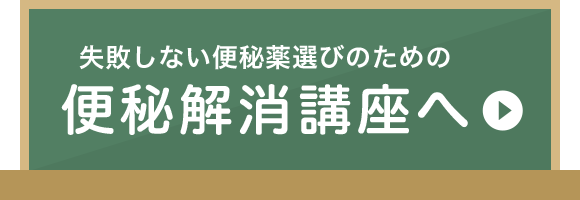VOL.171 【医師監修】食物繊維が多い食べ物を紹介!摂取量の目安も解説

食物繊維は便通を整える働きがあるといわれています。
便秘に悩んでいる方はとくに、食物繊維が多く含まれる食べ物は何か知っておきたいことでしょう。
今回は、食物繊維が豊富に含まれている食べ物や料理、摂取量の目安などを紹介します。日頃の食生活にぜひ取り入れてみてください。
食物繊維の種類と効果
食物繊維は小腸で消化・吸収されずに大腸まで行きつく栄養素の1つです。
不溶性食物繊維と水溶性食物繊維に分類され、働きや期待できる効果が異なるので、それぞれについて説明します。
不溶性食物繊維
不溶性食物繊維とは、その名のとおり水に溶けず、水分を吸収して膨らむ特徴があります。
便のかさを増す、つまり量を増やして、便通を良くする効果があるといわれています。
水溶性食物繊維
水溶性食物繊維とは、その名のとおり水に溶けるものですが、水に溶けるとねばねばする特徴を持ったものがあります。
腸内細菌に働きかけるので、腸内環境を整え、排出しやすい軟便を形成するといわれています。
また、胆汁酸を吸着して再吸収を防ぎ、血中コレステロールを下げる効果も期待できるといわれています。
食物繊維が多い食べ物・料理
ここからは、食物繊維が多い食べ物をご紹介します。
それぞれ不溶性か水溶性のどちらが多く含まれているかも解説しますので、バランス良く摂取するようにしましょう。
野菜
繊維質の硬い野菜や根菜、豆類は、不溶性食物繊維が多く含まれています。筋の少ない野菜やイモ類は、水溶性食物繊維が多く含まれています。
例えば、不溶性食物繊維を摂取するためにゴボウやにんじんなどの根菜のスープ、水溶性食物繊維を摂取するためにオクラとワカメの酢の物などが、さっぱりと食べられておすすめです。
また、鍋にすることで、不溶性と水溶性の両方を同時に手軽にたくさん摂取しやすいです。
果物
果物には水溶性食物繊維が多く含まれます。とくに、いちごやみかん、桃などです。
そのまま食べるほかに、腸内環境の改善も期待できるヨーグルトと混ぜても美味しく食べられます。
また、ドライフルーツも食物繊維が豊富だといわれており、よく噛んで食べるので満足感も得られやすいことが期待できます。間食の際は、ドライフルーツを取り入れるのもおすすめです。
穀類
穀類にも食物繊維が多く含まれます。
穀類の外皮にはとくに多くの不溶性食物繊維が含まれており、玄米ご飯や麦ご飯、胚芽米ご飯、全粒粉パンなどを積極的に摂取すると良いでしょう。
全粒粉パンをサンドイッチにしてレタスやトマトなどを挟めば、食物繊維が多く摂取できます。
キノコ類
キノコ類も不溶性食物繊維が多く含まれます。えのきやしめじ、しいたけなど、さまざまな種類があるため、料理にも使いやすいです。
きのこは味が淡白で合わせやすいため、煮物や炊き込みご飯、味噌汁など、さまざまな料理にプラスしてはいかがでしょうか。
食物繊維は1日にどのくらい摂取すれば良い?
成人は少なくとも 1 日当たり25gの食物繊維が必要といわれています(※)。
しかし、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)によると、ほとんどの方が、食物繊維の摂取量が不足しており、男性・女性ともに1日10~14gほどしか摂取できていないのが現状です。
摂取しているつもりでも、意識しないと不足していることが多いのかもしれません。
(※) 生活習慣病の発症予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量
食物繊維が不足するとどうなる?
食物繊維が不足すると体に不調が出る可能性があります。以下では食物繊維が不足すると、どのような症状が出る可能性があるのか解説します。
便秘になりやすくなる
食物繊維不足は便秘になる原因の1つです。例えば、不溶性食物繊維が不足すると便のかさが小さく、排便しにくくなります。便秘になるとお腹が張ったり、ガスが多くなったり、不快な症状が出ます。
便秘の予防には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方バランスよく取り入れる必要があります。
一方、不溶性食物繊維ばかりを摂っていると、便が硬く大きくなりすぎてしまい、排便しにくくなることもあるので、摂取するバランスが大切です。
生活習慣病に罹患するリスクが高まる
さまざまな研究などで、食物繊維の不足が生活習慣病の発症に関連するという報告が多くあります。
一方、食物繊維の摂取量が多いほど、生活習慣病の発症率や死亡率が低くなる傾向があるとの報告もあります。
例えば、生活習慣病のなかでは、コレステロールの低下が期待できるなどがあげられます。
専門機関の研究結果より、1日に25~29gの摂取でさまざまな生活習慣病の発症リスクが低下すると報告されています。
なお、厚生労働省からは、「少なくとも 1日当たり 25g」を食物繊維の目標量とされています。
出典:一般社団法人 日本家族計画協会 第4回「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会
食物繊維の摂取以外で便秘を改善する方法

便秘予防には、食物繊維を摂取する以外にもいくつか方法があります。食生活の改善はもちろん必要ですが、今すぐ始められる方法もあるため、以下で紹介します。
1日3食を規則正しく食べる
食事の時間を規則正しくすることが大切です。食事を規則的にすることで、胃腸の動きも規則的になり、排便のリズムも整いやすくなります。
栄養バランスのとれた食事を規則正しく摂り、生活リズムを整えることが大切です。
水分をこまめに摂取する
体内の水分が不足すると、便に含まれる水分も少なくなり、便が硬くなることで排便しにくくなります。
また、硬い便を無理に出そうとすると、いきむことによって体調が悪くなったり、痔を引き起こしたりするリスクもあります。
1日2リットルを目安に、一気に飲むのではなく、こまめに水分補給することを心がけましょう。
適度な運動をする
運動不足になると腸への刺激が減り、便秘の原因になります。
排便時には腹筋を使うため、筋力が低下していると便秘気味になることもあります。
いきなり無理をする必要はありませんが、ウォーキングやストレッチなど、少しずつ運動習慣を身につけると良いでしょう。
食物繊維を意識して食事のメニューを考えよう
食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があります。
2種類の食物繊維を意識的にバランスよく摂取することで、便秘改善につながる可能性があります。食事のメニューを選ぶときにも、2種類の食物繊維を意識して摂取してみましょう。
食物繊維を意識して食事をしても、便通が悪いと感じる方は、酸化マグネシウム便秘薬を試してみるのも1つの方法です。
酸化マグネシウム便秘薬はお腹が痛くなりにくく、クセになりにくいため、初めての方でも服用しやすいでしょう。ただし、ほかにお薬を飲んでいる方、持病がある方は薬剤師や医師に相談してから服用しましょう。
なお、健栄製薬の「酸化マグネシウ-ムE便秘薬」は、オンラインショップでも購入できます。仕事などで薬局へ行く余裕がない方は、ぜひ検討してみてください。
https://kenei-online.shop/collections/ebenpi
- 高山医師よりコメント
- 食物繊維は適切に摂ることで便秘の解消につながります。生活習慣病や死亡率にも影響があり適切な摂取を試みましょう。なお、手術などの既往がある方はかえって良くない場合もありますので、主治医の先生によくご相談ください。
- 監修者
-

医師:高山 哲朗
かなまち慈優クリニック 理事長
平成14年慶應義塾大学卒業、慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長。医学博士。日本内科学会総合内科専門医。日本消化器病学会専門医。日本消化器内視鏡学会専門医。日本医師会認定産業医。東海大学医学部客員准教授。予測医学研究所所長。