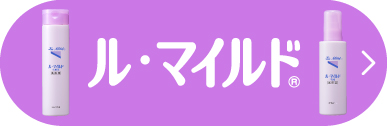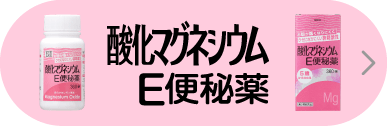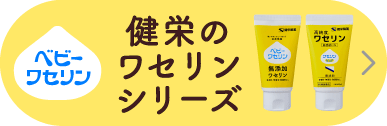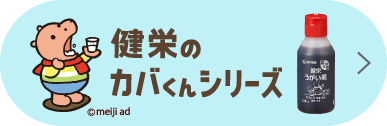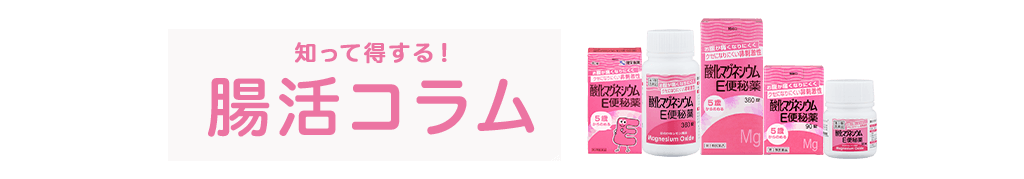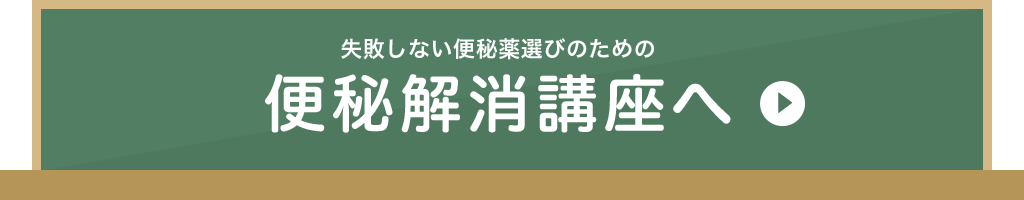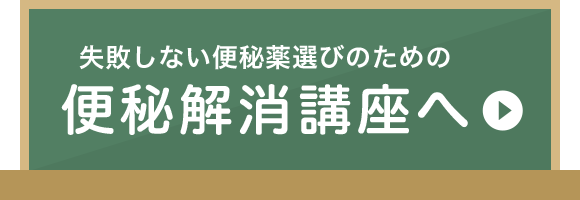VOL.83 便が出ないのは病気の影響?考えられる疾患と便秘の改善方法を紹介

便が出ない状態が続くと、腹痛などの体調不良を訴える方も多く見られます。
便秘にはさまざまな原因がありますが、病気が隠れている可能性もあるため、長期間便が出ない状態を放置するのは危険です。
今回は、便が出ない原因や便秘の際に考えられる病気について説明します。
あわせて、病気以外で便が出ない場合に、日常生活で取り入れられる対処法も紹介するため、便が出ない状態が続いている方は参考にしてください。
便が出ない場合に病院で受診する基準は?

便が出ない場合、「何日以上排便がない場合は便秘」という明確な定義はなく、排便回数が多くても排便量が少ない場合は便秘と判断されることもあります。そのため、便が出ない状況が続いたときには、受診すべきか判断に迷うかもしれません。
しかし、便秘の症状が長引いている場合や症状が重い場合は、何らかの病気が原因の可能性もあります。
便秘の原因が病気である場合は、まずはその基礎疾患を早急に治療することが大切です。便秘以外にも気になる症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。
便が出ないときに考えられる病気
便が出ない状態が続いている場合は、大腸の病気が関係している可能性があります。長期化している場合や、お腹周りに痛みがあるなど異常が感じられる場合は、医療機関へ相談しましょう。
便が出ないときに疑われる、代表的な3つの病気は以下のとおりです。
- ・大腸がん
- ・潰瘍性大腸炎
- ・過敏性腸症候群
それぞれの病気について詳しく解説します。
大腸がん
大腸がんとは、大腸の内側の粘膜に発生する腫瘍です。早期の場合は自覚症状がほとんどないことが多いです。
しかし、進行すると血便や体重減少、便通異常といった症状が現れてきます。
便が出ないこと以外にも何か症状がある方は、医療機関で詳しく検査を受けてみましょう。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜が慢性的に炎症を引き起こし、潰瘍などが生じる病気です。その発症原因は明確にはわかっていません。
潰瘍性大腸炎の主な症状は、血性下痢や粘血便、腹痛などです。また、疲れやすい、貧血、発熱、体重減少などの症状が出ることもあります。
便が出ないことに加えて、このような症状がある場合は医療機関を受診しましょう。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは、腹部膨満感や腹痛、下痢や便秘などの症状を伴う病気です。
大腸を検査しても、炎症や潰瘍、内分泌異常が認められず、原因は十分に解明されていません。何らかの原因で腸が過敏になることで発症すると考えられています。
病気以外で便が出ないときに考えられる原因
病気以外で便が出ない原因として考えられるのは、大きく分けて以下の3つです。
- ・水分や食物繊維の不足
- ・運動不足などの生活習慣
- ・服用している薬の副作用
それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。
水分や食物繊維の不足
水分や食物繊維が不足すると、便が出ないことが続く場合があります。
水分不足になると便が硬くなり、排出が困難になります。食物繊維には便のかさを増やし、やわらかくする作用があるため、不足すると便が小さく硬くなり、排便がしにくくなる傾向があります。
運動不足などの生活習慣
運動不足が続くと血流が悪くなり、便が出ない状態を引き起こしやすくなります。運動不足は血流を悪くするだけでなく、筋力低下により腸の動きを鈍らせてしまいます。
とくに、デスクワークが多い方や、同じ姿勢を長時間続けている方は、慢性的な運動不足になりやすいため注意が必要です。休憩時間などを活用して意識的に体を動かし、全身の血流を促進するとともに、筋力を維持できるようにしましょう。
また、便秘はストレスで引き起こされる場合があります。便が出ない状態が続く方は、運動不足やストレスが溜まっていないか、生活習慣を見直してみると良いでしょう。
服用している薬の副作用
服用している薬によっては、副作用で便が出にくくなることがあります。薬の副作用による便秘は「薬剤性便秘」と呼ばれます。
薬剤性便秘の原因となる薬にはさまざまなものがあります。複数の薬を服用していて、便秘が薬の副作用による可能性がある方は、医師や薬剤師に相談すると良いでしょう。
なお、医療機関に相談する前に自己判断で薬の服用を中止することは避けましょう。
便が出ないときの改善方法
「何日間便が出ないと便秘」という明確な定義はありません。
しかし、便が出ない状態が長引くことで体調に悪影響が出てしまうことがあります。不快な症状を解消するためにも、以下の改善方法を試してみてください。
- ・市販の便秘薬を試してみる
- ・栄養バランスのとれた食事を心がける
- ・生活習慣を見直す
- ・十分な睡眠をとる
市販の便秘薬を試してみる
便が出ないときに排便を促す方法として、便秘薬を試してみるのも良いでしょう。便秘薬にはさまざまな種類がありますが、とくに、酸化マグネシウムの便秘薬はクセ(習慣性)になりにくく、お腹に刺激が少ないのが特徴です。
健栄製薬の「酸化マグネシウムE便秘薬」は、オンラインショップでも販売されています。ドラッグストアに行く時間のない方などは、ぜひ検討してみてください。
なお、薬は使用上の注意を確認した上で、用法・用量を守って服用しましょう。便秘薬を試しても便が出ない症状が改善されない場合や、便秘以外の症状で気になることがある場合は、早めに医療機関を受診してください。
栄養バランスのとれた食事を心がける
便秘を解消するには、食生活の見直しも大切です。とくに、食物繊維を豊富に含む食材を積極的に摂取しながら栄養バランスを整え、排便を促す食生活を心がけましょう。
また、便が出ない原因の1つでもある水分不足を防ぐために、意識的にこまめな水分補給を行うことも大切です。
生活習慣を見直す
運動不足にならないよう、日常的に適度な運動を取り入れましょう。ウォーキングやストレッチなど、気軽にできる運動がおすすめです。マッサージや腹部を温めることも便秘解消効果が期待できるため、組み合わせて行いましょう。
生活リズムを整えることも大切です。排便のリズムを作るために、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけましょう。朝食をしっかり摂り、トイレに行ける時間を確保すると排便リズムも整います。
ストレスは便秘の要因となるため、意識的に発散するよう心がけましょう。適度な運動や規則正しい生活リズムは、ストレスの緩和にもつながります。ストレスが解消され生活リズムが整うと、自律神経も整い腸の働きが良くなります。
十分な睡眠をとる
副交感神経が優位になると、腸のぜん動運動が活発になるといわれています。副交感神経が優位になるのは、睡眠中など心身がリラックスしているときです。
そのため、便が出ない状態が続くときには、十分に睡眠時間を確保してゆっくり休むことを心がけましょう。リラックスして腸が働きやすくなることで、翌朝の排便を促す効果が期待できます。
便が出ない原因は病気の可能性も!疑われる場合は医療機関で受診しよう
便が出ない状態が続いている場合でも、市販の便秘薬を試したり、生活習慣を見直したりすることで解消される可能性があります。まずはご自身の生活を見直し、できることから試してみましょう。
しかし、便が出ないだけでなく、ほかにも気になる症状がある場合は、病気が原因の可能性も考えられます。
改善方法を試しても便が出ない状態が続く場合は、自己判断せず早めに医療機関に相談しましょう。