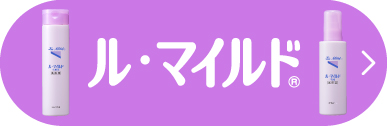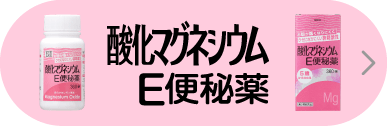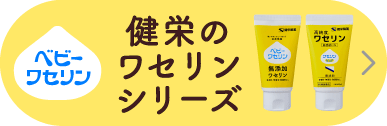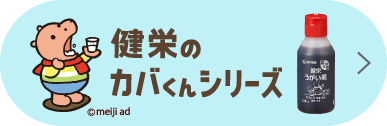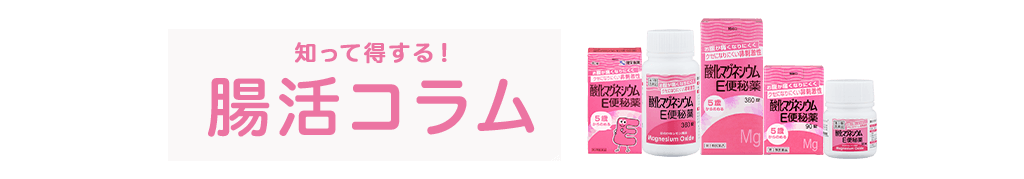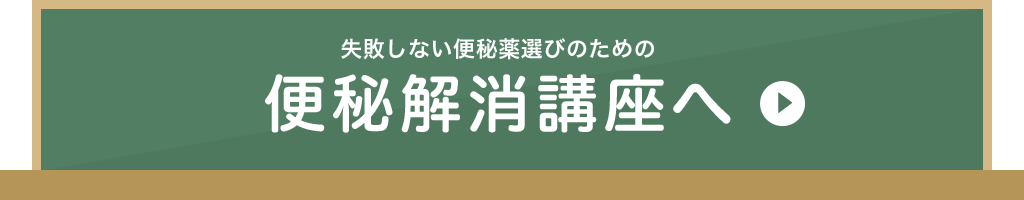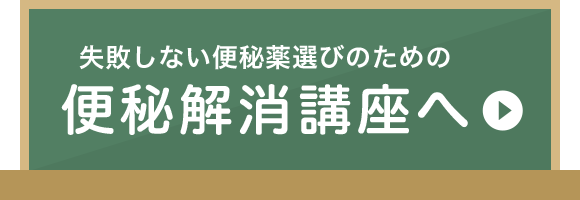VOL.100 生理前後に便秘となる原因は?日頃から取り組める対策方法も紹介

「生理前になると排便の回数が減る」「生理が終わってもすっきりしない感じが続く」そんな便通の変化を経験したことがある方もいるかもしれません。
生理前後の便秘は、女性ホルモンの変化が深く関係しており、体調が不安定になりやすい時期です。腸の動きにも影響が出やすく、便秘を引き起こす原因になることもあります。
今回は、生理前後に便秘が起こる原因と、日常生活で実践できる対策法について解説します。生理前後の便秘に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
生理前・生理後に便秘となる原因
生理の前後は、ホルモンバランスの変化によって便通が乱れやすくなる時期です。ただし、生理前と生理後では体内のホルモンの状態が異なるため、便秘の原因にも違いが見られます。
以下では、それぞれの時期に起こりやすい体の変化と、便秘につながるメカニズムについて詳しく解説します。
生理前|黄体ホルモン(プロゲステロン)の影響
生理前に便秘になるのは、排卵日から生理まで多く分泌される黄体ホルモンの影響が大きいと考えられています。黄体ホルモンは女性ホルモンの一種で、プロゲステロンとも呼ばれ、排卵後に卵巣から分泌されます。
この黄体ホルモンは、腸の平滑筋の刺激を感知する力を弱め、便の水分を吸収して硬くする働きがあります。また、黄体ホルモンの分泌が多くなると、排便を促す腸のぜん動運動が低下するため、生理前は便秘になりやすい傾向です。
イライラしやすくなる、感情の起伏が激しくなる、食欲が増すなど、さまざまな症状が現れることも少なくありません。これらの症状をPMS(月経前症候群)と呼びます。
黄体ホルモンの影響によって引き起こされる便秘は、PMS(月経前症候群)の症状の1つです。
生理中・生理後|ホルモンバランスや自律神経の乱れなど
通常、生理が始まる頃には、便秘の原因とされる黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌が減少し、腸の動きが徐々に回復するといわれています。そのため、生理が始まると便通が改善する方が多く、なかには下痢気味になる方もいます。
ただし、ホルモンバランスが乱れている場合には、生理中や生理後も黄体ホルモンの影響で腸の働きが低下し、便秘が継続することがあります。
また、生理に伴う体調の変化やストレスによる自律神経の乱れが原因で、腸のぜん動運動が鈍くなり、便秘が長引くことがあります。
生理後も便秘が続く主な原因
生理後も便秘の状態が続く場合、ホルモンバランスの影響に加えて、以下のような日常生活の要因が関係することがあります。
- ・ストレス
- ・食生活の乱れ
- ・水分不足
- ・常用薬の影響
それぞれの要因を詳しく解説します。
ストレス
ストレスを強く感じると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。自律神経は腸の動きと深く関わっており、自律神経が乱れることでぜん動運動が低下し、腸内の便の移動が妨げられることもあります。
とくに、日常的に精神的ストレスを抱えている方や、緊張・イライラしやすい方は、腸の働きが不安定になりやすい傾向です。
さらに、生理中は生理痛や体調不良、経血による不快感に加え、ナプキンの交換や漏れへの不安など、心身にかかるストレスが多くなる時期です。こうしたストレスによって自律神経の乱れが強まり、便秘が長引くこともあります。
食生活の乱れ
丼ものやパスタなど炭水化物中心の食事が多かったり、野菜が不足していたりすると、食生活の乱れが原因で便秘になることがあります。とくに、食物繊維が不足すると、便秘になりやすいです。
生理中や生理前後に食事が偏ってしまう方は多いかもしれません。偏った食事を続けると、便秘が悪化するおそれがあります。
また、食事量を減らすダイエットを継続している方も便秘のリスクに注意が必要です。直腸を刺激するために十分な量の便が作られないと、排便のきっかけとなる反射が起こりにくくなるため、便秘が続きやすくなります。
水分不足
便の主成分は水分です。体の水分が不足すると便が硬くなり、便秘を引き起こしやすくなります。
水分の摂取量が少ない方や、摂取していても汗をかきやすい方は、体の水分が不足しやすく、便秘のリスクが高まるため注意が必要です。
常用薬の影響
生理の症状によって薬を服用する方は多いかもしれません。薬のなかには、服用によって便秘が起こりやすくなるものもあります。
ただし、全ての方に同じような症状が現れるわけではなく、体質や薬との相性によっても変わります。
もし、飲んでいる薬が便秘の原因かもしれないと感じた場合は、自身の判断で服用を中止せず、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
生理前・生理後の便秘に対して日頃からできる対策方法

生理前に女性が便秘になりやすくなるのは、黄体ホルモンの影響が大きいため、対処が難しいかもしれません。
しかし、なるべく便秘に悩まない体質を目指すには、普段から食生活に気をつけたり、排便習慣をつけたりすることが大切です。
ここでは、日常で取り入れられる便秘の対策方法を紹介します。
水分をこまめに摂る
便秘になりにくい体質を目指すには、普段からこまめに水分を摂取することが大切です。水分を十分に摂ると便が柔らかくなり、カサも増すため排便がしやすくなります。
とくに、いつも便が硬くて排便が困難な方は、水分不足の可能性があります。普段から水分の摂取量を意識し、1日2リットルを目安に水分補給を心がけるとよいでしょう。
また、水分を摂取する際は、なるべく水か白湯にすると良いです。カフェインが含まれるお茶やコーヒーは利尿作用があり、摂取した水分が尿として排出されやすくなってしまいます。
バランスの良い食事を心がける
生理前の便秘を予防するためにも、普段からバランスの良い食事を心がけることが大切です。
主食、主菜、副菜を基本とし、1日3食を規則正しく食べることを意識しましょう。とくに、便秘解消が期待できる食物繊維を意識して摂取することが効果的です。
食物繊維は「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」の2つに分類されます。
水溶性食物繊維は、腸内環境を整えてくれる善玉菌のエサになり、不溶性食物繊維は便に水分を蓄え柔らかくする役割を担っています。
水溶性食物繊維は海藻類や山芋、こんにゃくなどに、不溶性食物繊維は大豆やキノコ類に多く含まれています。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を含むものをバランス良く摂るようにしましょう。
また、大腸に刺激を与える脂質を適度に摂取することも重要です。さらに、腸内環境の改善が期待できる発酵食品やオリゴ糖を含む食品も取り入れると良いでしょう。
ストレスを溜め込まない
ストレスによって自律神経が乱れ、交感神経が優位になると、腸のぜん動運動が抑制されるため、便秘につながりやすいです。
腸の動きが活発になるのは、副交感神経が優位なときです。副交感神経はリラックス時や睡眠時に優位になりやすいため、日頃からリラックスできる時間を意識的につくると良いでしょう。
軽い運動をする、好きな音楽や映画を楽しむ、日光を浴びながら散歩をするなど、心身をリラックスさせる活動を取り入れるのもおすすめです。
また、毎日決まった時間に就寝し、質の良い睡眠を確保することも自律神経の安定につながります。
ストレスは女性ホルモンの分泌にも影響を与えるため、ホルモンバランスを整える観点からも、ストレスを上手に発散する習慣を持つことが大切です。
体を温める
体が冷えると、胃腸の働きが鈍くなり、便秘につながることがあります。とくに、女性は筋肉量が少なく、冷えを感じやすいため、腸の動きが低下しやすい傾向です。
便秘を予防・改善するためにも、日頃から体を温める「温活」を意識すると良いでしょう。以下のような冷え対策を日常に取り入れることをおすすめします。
- ・腹巻きやカイロでお腹を温める
- ・温かい食事や飲み物をとる
- ・40℃前後の湯船にゆっくり浸かる習慣をつける
- ・手足や首まわりを冷やさない服装を心がける
- ・夏でも冷房対策として、薄手の羽織りものやひざ掛けを用意しておく
こうした方法で体の内側と外側から温めることで、腸の働きが整いやすくなります。
冷えはホルモンバランスの乱れとも関係するため、冷え対策は女性ホルモンの安定にもつながる可能性があります。体調管理の一環として、無理なく続けられる温活を生活に取り入れましょう。
適度な運動を心がける
日常生活に適度な運動を取り入れることで、腸の働きが促され、便通の改善が期待されます。
一方で、運動不足が続くと腸の動きが鈍くなり、便秘の原因につながることがあります。
とくに、おすすめとされる運動は以下のとおりです。
- ・ウォーキング
- ・水泳
- ・ジョギング
- ・ヨガ
これらの運動は血行を促進し、腸のぜん動運動を活発にする効果があります。加えて、ストレスの軽減や生活リズムの安定にもつながり、心身のバランスを整える効果も期待できます。
運動に慣れていない方は、まずは短時間でできる運動から始めてみるのがおすすめです。
市販の便秘薬を試してみる
日常生活でできる便秘対策で効果が見られない場合には、市販の便秘薬を取り入れてみるのも良いでしょう。
なかでも、酸化マグネシウムを主成分とする便秘薬は、便をやわらかくして自然な排便を促す作用があり、お腹が痛くなりにくく、クセになりにくいとされています。
なお、健栄製薬の酸化マグネシウム便秘薬は、公式オンラインショップでも取り扱いがあります。自宅にいながら手軽に購入できるため、ぜひ検討してみてください。
ただし、服用する際は使用上の注意をよく読み、不安な点があれば医師や薬剤師に相談するようにしてください。
生理前・生理後の便秘で悩まない体質を目指そう!
生理前・生理後の便秘には、ホルモンバランスや自律神経の乱れなど、女性の体ならではの変化が関係すると考えられます。
生理のたびに便秘の不快感に悩まされている方は、日頃の生活習慣を少し見直すだけでも、腸の調子が整いやすくなるかもしれません。
こまめな水分補給や食物繊維を意識した食事、ストレスをためない工夫、冷え対策、適度な運動など、できることから無理なく続けていくことが大切です。
それでも改善が見られないときは、市販の便秘薬を試してみるのも1つの方法です。
生理と上手につき合いながら、少しずつ便秘に悩まない体づくりを目指しましょう。