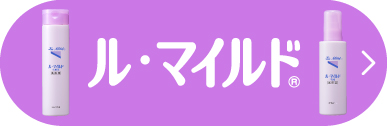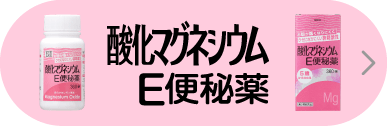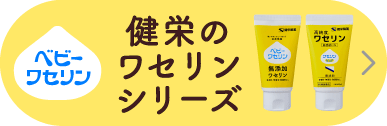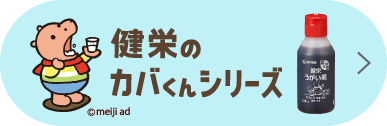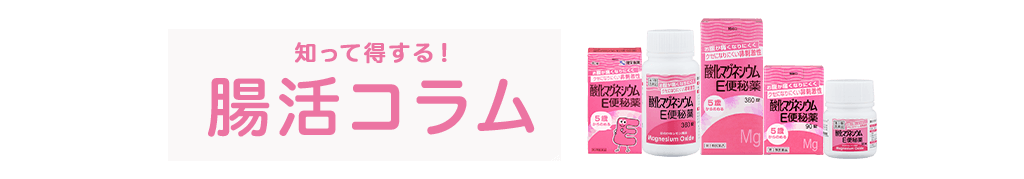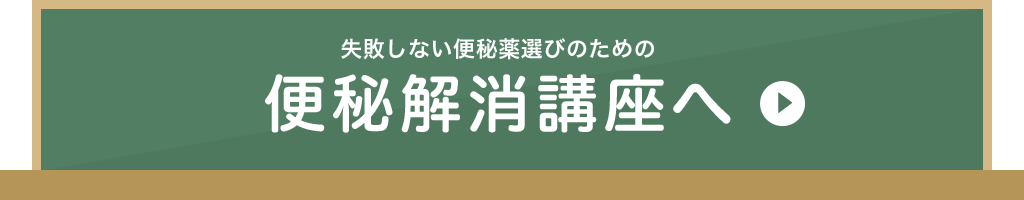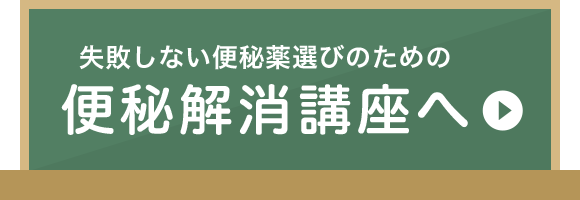VOL.120 たけのこに含まれる栄養と効能とは?1日の摂取量目安と注意点を解説

春から初夏の味覚として人気のたけのこは、炒め物や煮物、炊き込みごはんなど、さまざまな料理に使える食材です。
そして、便通を促進する食物繊維やカリウムなどの栄養素が豊富に含まれているのも特徴です。
今回は、たけのこの栄養素や1日の摂取量などを解説します。たけのこに含まれる栄養素や適切な摂取量を理解し、無理なく食卓に取り入れることで、体調管理に役立つでしょう。
たけのこの効能を活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
たけのこに含まれる栄養素
たけのこに含まれている主な栄養素は以下のとおりです。
| 栄養素 | 特徴 |
|---|---|
| タンパク質 | 臓器や筋肉の構成成分となる、人間の体に欠かせない栄養素 |
| カリウム | 体の中の余分な塩分を排出する働きに期待ができる栄養素 |
| チロシン | ドーパミンと呼ばれる神経伝達物質を合成するために必要な栄養素 |
| 食物繊維 | 便を作るための大切な栄養素 |
それぞれの栄養素を詳しく解説していきます。
タンパク質
タンパク質は、筋肉や内臓、皮膚、髪の毛など、体のあらゆる組織をつくる栄養素であり、酵素やホルモン、免疫物質の材料にもなります。数ある栄養素のなかでも、体にとって大切な存在です。
タンパク質は、不足すると免疫力の低下や筋力の減退につながるおそれがある一方、過剰に摂りすぎると腎臓に負担がかかることもあります。
理想的なのは、肉や魚などの動物性タンパク質と、大豆製品や野菜などの植物性タンパク質をバランス良く摂取することです。
ちなみに、茹でたたけのこには100gあたり約3.5gのタンパク質が含まれており、植物性タンパク質の補給源として期待できます。
カリウム
カリウムは、成人の体内におよそ120〜200g存在するとされ、その多くは細胞の中に含まれています。ナトリウムとともに、体の水分バランスや浸透圧の調整、神経の伝達、筋肉や心臓の正常な働きを支える重要なミネラルです。
不足すると筋力の低下や脱力感などを引き起こすおそれがある一方、過剰に摂りすぎると心臓に影響を及ぼすリスクがあります。腎機能が低下している方は、体内にカリウムが蓄積しやすくなるため、摂取には注意が必要です。
たけのこには、茹でた状態で100gあたり約470mgのカリウムが含まれています。カリウムを補う食材の1つとして活用できるでしょう。
チロシン
チロシンは、たけのこに多く含まれるアミノ酸の一種です。茹でた際に、切り口や節の部分に白く現れる結晶状の物質がチロシンで、うまみ成分としても知られています。
チロシンは、神経伝達物質であるドーパミンやアドレナリン、さらには甲状腺ホルモンの材料となる重要な栄養素です。脳の働きを活性化させる働きがあるとされており、やる気や集中力をサポートする効果も期待できます。
茹でたけのこについた白い物質を洗い流す方も多いかもしれませんが、栄養を損なわないためにも、そのまま食べるのもおすすめです。ちなみに、生のたけのこ100gには、約180mgのチロシンが含まれています。
食物繊維
食物繊維は、腸内環境を整え、便通を促す上で欠かせない栄養素です。大きく分けて、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けにくい「不溶性食物繊維」の2種類があります。
不溶性食物繊維は、便のかさを増やして腸を刺激し、排便を促進する働きがあります。一方、水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなって腸内フローラを整えるほか、便に水分を与えてやわらかくする作用もあります。
食物繊維は便秘の予防や改善にも役立つとされており、日々の食事で意識して摂ることが望ましいです。茹でたけのこに含まれている食物繊維は、100gあたり約3.3gです。
便秘改善にたけのこが注目される理由
たけのこに含まれている食物繊維の多くは、不溶性食物繊維です。キャベツやレタスよりも多くの食物繊維を含んでおり、調理のアレンジもしやすいです。
炒め物や煮物、和え物など、さまざまな料理に取り入れられるため、日々の食卓にプラスすると良いでしょう。
なお、厚生労働省の「食物繊維の必要性と健康」によると、現代の日本人の多くは食物繊維の摂取量が不足していると考えられています。
春から初夏にかけて旬を迎えるたけのこを、日々の健康づくりに役立ててみましょう。
1日に摂取するたけのこの目安量
食物繊維は、成人男性で1日21g以上、成人女性で18g以上摂取するのが望ましいとされています。
現代の日本人の平均的な食物繊維の摂取量は13g前後といわれているため、男女ともに食物繊維が不足している可能性があります。
便秘の改善を目指すためにも、食物繊維は意識して摂取しましょう。厚生労働省では性別に関係なく、まずは1日3~4gの食物繊維を食事にプラスすることを推奨しています。
たけのこに含まれている食物繊維は100gあたり約2.8gであるため、1日の食物繊維摂取量を3~4g増やすには、たけのこを150~200g摂取する必要があります。
ただし、1食でたけのこを150~200g摂取するのは難しいため、3食に分けて取り入れたり、食物繊維が豊富なほかの食材と組み合わせたりしましょう。
疾患によっては、たけのこの摂取が望ましくない場合もあるため、持病をお持ちの方は医師に相談してから食事に取り入れてください。
また、食物繊維だけに栄養が偏るのも良くありません。健康を維持するためには、ご飯やパンなどの主食、味噌汁やサラダなどの副菜、肉や魚をはじめとするタンパク質を多く含む主菜を、バランス良く摂取することが大切です。
牛乳やヨーグルト、チーズなどの乳製品も、健康には欠かせない栄養素を含んでいるため、デザートや飲み物として食事に取り入れてみましょう。
たけのこの食べ過ぎには注意しよう
不溶性食物繊維が豊富なたけのこは、便通をサポートする食材ですが、消化に時間がかかるため、胃腸が弱い方や下痢をしやすい方は食べすぎに注意しましょう。
また、不溶性食物繊維をとりすぎると、便秘のタイプによってはかえって悪化することもあります。海藻類や果物などに含まれる水溶性食物繊維とバランス良く摂ることが大切です。
さらに、たけのこはアクが強く、一度に大量に摂取すると、かゆみやじんましんなどアレルギーに似た症状が出ることもあります。
たけのこが持つ健康へのメリットを活かすために、適量の摂取を心がけましょう。
たけのこ以外で便秘改善を目指す方法

たけのこの摂取だけで便秘改善を目指すのではなく、便秘の原因を1つずつ見直し、解消していくことが大切です。
便秘は生活習慣が原因となっている場合もあるため、以下4つのポイントを参考に便秘改善に努めましょう。
- ・バランスの良い食事を摂る
- ・運動習慣をつける
- ・規則正しい生活を送る
- ・酸化マグネシウム便秘薬を試してみる
以下で詳しく解説します。
バランスの良い食事を摂る
偏った食事を継続すると、便秘の原因となるだけでなく、体全体にも悪影響を及ぼすおそれがあります。まずは日々の食事内容を見直し、健康的な食習慣を身につけましょう。
便秘の改善に欠かせないのは、食物繊維の摂取です。それぞれ異なる働きをする水溶性食物繊維と不溶性食物繊維を、バランス良く摂取することがポイントです。
水溶性食物繊維は、わかめ、きのこ類、ごぼう、納豆などに多く含まれています。一方、不溶性食物繊維は、たけのこのほか、玄米やさまざまな野菜類に多く含まれています。
さらに、腸内環境を整えるには、善玉菌を増やす食材を意識的に摂取することも重要です。善玉菌を増やすための重要な要素は、乳酸菌とオリゴ糖です。
ヨーグルトやチーズなどに含まれる動物性乳酸菌、味噌やしょうゆ、キムチなどに含まれる植物性乳酸菌は、腸内の善玉菌をサポートするのに役立ちます。
また、オリゴ糖にも善玉菌の増殖を促す作用が期待できるため、甘味料として取り入れると良いでしょう。
ダイエットなどで過度に食事量を減らすと、便の量も減って排便が困難になる場合があります。無理な制限をせず、適切な量をしっかり摂ることも、便秘改善には欠かせません。
運動習慣をつける
運動をすると全身の血行が促進され、便通も良くなる傾向があります。運動不足で便秘を繰り返している方は、この機会に運動習慣を身につけましょう。
いきなりハードな運動をする必要はありません。散歩やウォーキング、水泳やヨガなど、毎日無理なく続けられる運動を行ってください。全身運動は1回に20分ほど、週に3~4回行うのが理想です。
可能であれば、全身運動と腹筋運動を組み合わせてエクササイズするのがおすすめです。腹筋が弱いと排便時にうまく腹圧がかからないため、筋力を強化するとスムーズに排便できる可能性があります。
腹筋運動は腹部の血行を良くする効果も期待できるため、お腹が冷えやすい方にも向いています。運動が苦手な方は、無理のない範囲でできることから始めましょう。たとえ短時間でも、継続することが大切です。
規則正しい生活を送る
生活習慣が乱れると、自律神経のバランスも崩れやすくなります。自律神経の不調は、腸の動きが乱れ、排便リズムが不安定になることがあります。そのため、まずは規則正しい生活を意識することが大切です。
毎日しっかりと睡眠を取り、生活リズムを整えることで、自律神経の働きが安定しやすくなります。生活が不規則な方は、まずは就寝・起床時間を整えることから始めましょう。
また、朝のルーティンを作るのもおすすめです。例えば、起きてすぐにコップ1杯の水を飲み、朝食をしっかり摂ることで、腸の動きの活性化が期待できます。排便リズムを整えるために、毎日同じ時間にトイレに入るのもポイントです。
さらに、ストレスも自律神経を乱す要因となるため、意識的にリフレッシュする時間を取り入れましょう。アロマの香りに癒やされたり、映画を観てリラックスしたりするなど、自身が心地良いと感じる方法で構いません。
酸化マグネシウム便秘薬を試してみる
便秘に悩んでいる方にとって、酸化マグネシウム便秘薬は優れた選択肢の1つです。酸化マグネシウム便秘薬は、腸内の水分を引き寄せて便をやわらかくし、自然に近い形で排便を促します。
お腹が痛くなりにくく、習慣性も少ないのが特徴です。5歳以上の子どもや妊娠中の方、高齢者にも使用が可能とされており、比較的使いやすい便秘薬といえるでしょう。
ただし、はじめて使用する方や、ほかの薬を服用している方、持病がある方は、事前に医師または薬剤師に相談しましょう。
なお、酸化マグネシウム便秘薬は、健栄製薬のオンラインショップ でも購入できます。便秘解消の選択肢の1つとして購入をご検討ください。
便秘以外にも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
食物繊維は食べ過ぎにも注意!たけのこを食事にプラスして便秘を予防しよう
たけのこには、便通をサポートする不溶性食物繊維をはじめ、カリウムやチロシン、タンパク質など、体に良い栄養素が含まれています。風味にクセがなくレシピも豊富で、食卓に取り入れやすい食材です。
ただし、たけのこに含まれる不溶性食物繊維を摂りすぎると、人によってはお腹の張りや便秘の悪化を招く可能性があるため、適量の摂取を心がけることが大切です。
食事がたけのこだけに偏らないよう、食物繊維を含むさまざまな食材と組み合わせて便秘を予防しましょう。