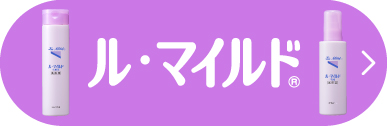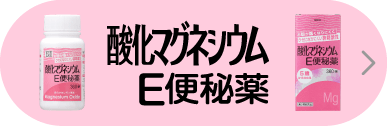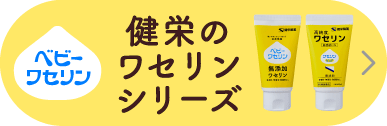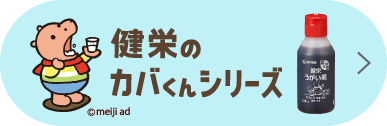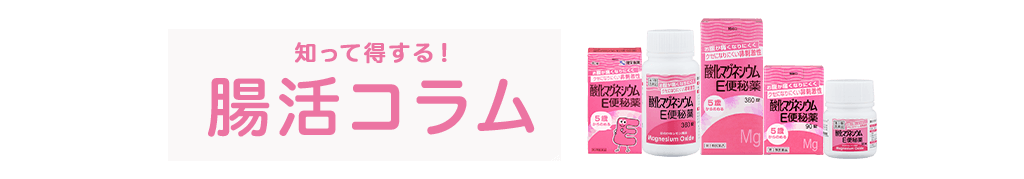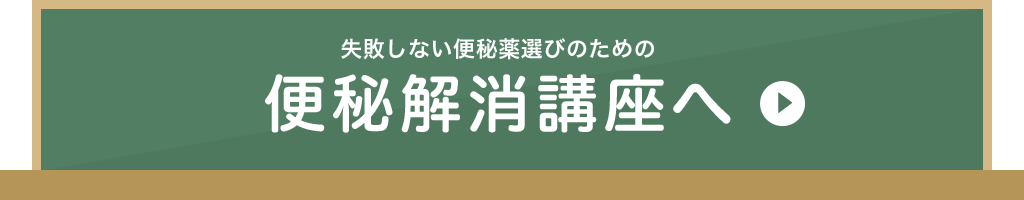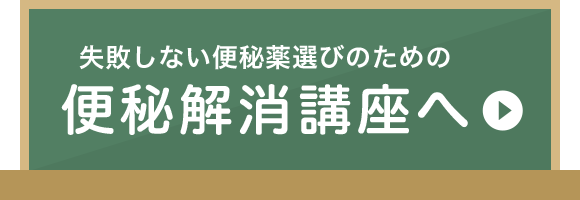VOL.4 便秘薬の種類を紹介|解消するための方法もあわせて解説

つらい便秘の症状をやわらげたい場合には、便秘薬が役立ちます。しかし、便秘薬にはさまざまな種類があるため、初めて使用する場合は選び方に悩むかもしれません。
今回は、代表的な便秘薬の種類を紹介します。また、便秘を根本から解消するために、薬を使用するほかに心がけたいこともあわせて解説します。便秘でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
主な便秘薬の種類
便秘薬にはさまざまな種類があります。新しいタイプの薬も登場していますが、現在主流なのは「非刺激性下剤(機械性下剤)」と「刺激性下剤」の2タイプです。
また、飲み薬とは異なる「座薬」も便秘薬に含まれます。それぞれの特徴と期待できる効果を紹介します。
| 非刺激性下剤(機械性下剤) | ●塩類下剤(浸透圧性下剤) ●膨張性下剤 ●糖類下剤 |
| 刺激性下剤 | ●大腸刺激性下剤 ●小腸刺激性下剤 |
| 坐薬 | - |
非刺激性下剤(機械性下剤)
加齢やダイエットによる食事制限などで食事量が不足し、排便に必要な量の便が作れないことが原因で起こる便秘に対して処方されます。
腸を刺激せず、便自体の水分量を増やして柔らかくすることで、排便を促す便秘薬です。成分によって「塩類下剤」「膨張性下剤」「糖類下剤」などに分類されます。
塩類下剤(浸透圧性下剤)
塩類下剤には、酸化マグネシウムが用いられた便秘薬があげられます。
「塩類下剤」はマグネシウムが主成分の薬で、昔から広く使用されています。長期にわたって服用しても、効果が弱まるような習慣性がほとんどありません。
ただし、高齢者や腎臓に疾患がある方は、服用法を誤ると「高マグネシウム血症」を引き起こす可能性があります。用法・用量を正しく守り、適切な使用を心がけましょう。
代表的な薬:酸化マグネシウム便秘薬
膨張性下剤
「膨張性下剤」は食物繊維のように薬自体が水分を吸収して便のカサを増やし、排便を促す薬です。作用が緩やかで習慣性が低く、自然な状態に近い排便を促します。
代表的な薬剤:カルメロース(カルボキシメチルセルロース)、プランタゴ・オバタ種子
糖類下剤
「糖類下剤」は、「塩類下剤」と同様に便の水分量を増やして柔らかくし、排便を促す薬です。
効果にはやや個人差がありますが、腸から吸収されない糖でできているため、甘味があり飲みやすく、乳幼児用の便秘薬としても用いられています。
代表的な薬剤:ラクツロース、D-ソルビトール
刺激性下剤
大腸や小腸などを直接刺激し、ぜん動運動を促して排便を促す薬です。
下剤としての効果が高く、加齢や運動不足、ストレスなどで腸の運動が低下する「弛緩性便秘」の解消に役立ちます。
ただし、長期にわたり服用すると耐性が生じ、効きにくくなることがあるため注意が必要です。刺激性下剤には大きく分けて「大腸刺激性下剤」「小腸刺激性下剤」の2種類があります。
大腸刺激性下剤
「大腸刺激性下剤」は主に大腸へ作用します。大腸の働きが低下し、排便しにくい高齢者に適した薬です。
代表的な薬剤:センノシド(センナ)、ピコスルファートナトリウム水和物
小腸刺激性下剤
「小腸刺激性下剤」は小腸を刺激するタイプの薬です。
現在、下剤としてはあまり使用されていませんが、食中毒や食あたりなどの際に使用されることがあります。
代表的な薬剤:ヒマシ油
坐薬
「坐薬」は肛門に直接入れて使用する薬で、直腸の肛門に近い部分に作用します。直腸に便が詰まっている場合や、飲み薬が使用できない際におすすめです。
即効性がある反面、過度な使用により自然な排便が得られにくくなるため、安易な使用は控えたほうが良いでしょう。
代表的な薬剤:炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム、ビサコジル
妊娠中や授乳中に使用できる便秘薬は?
妊娠中や授乳中は、大きくなった子宮や体内ホルモンの変化による影響を受け、食生活に気をつけていても便秘になりやすい時期です。とくに妊娠中の女性は、約半数が便秘になるとされています。
妊娠中や授乳中の方には、一般的に副作用が少ない「酸化マグネシウム」を主成分とした便秘薬が用いられます。
しかし、妊娠中や授乳中は赤ちゃんへの影響も考える必要があるため、薬の服用には十分に気をつけなければなりません。便秘薬を服用する前に、まずはかかりつけの産婦人科へ相談しましょう。
また、医療機関などで便秘の相談をすると、体への負担が少ない運動や生活習慣改善を受けられる場合もあります。
便秘薬の処方以外に病院で便秘を治療する方法

便秘で医療機関を受診する場合、一般的には胃腸科で診察を受けます。
しかし、慢性的な便秘やほかの症状を伴う場合は、病気が原因の可能性もあるため、内科への受診を検討してください。
なお、消化器内科は、一般的に胃や腸、肝臓などの消化器疾患を扱う診療科のため、便秘が診療対象かどうかを事前に電話などで確認してから受診しましょう。
また、便秘を専門的に治療する「便秘外来」もあります。大学病院などの大きな医療機関のほか、胃腸科や肛門科の専門医院に設置されている場合もあります。
病院では、便秘薬や整腸剤の処方のほか、便秘の症状が重い場合は浣腸や摘便が行われることもあります。
整腸剤を服用すると腸内細菌のバランスが整うため、便秘や下痢などの症状が改善されやすくなります。
浣腸は、便が肛門近くの直腸で固まっているタイプの便秘に適した医療行為です。肛門から薬剤を直接注入することで腸を刺激し、排便を促します。
即効性がある一方で、急激な排便に伴い血圧低下を引き起こすことがあるため、高齢者には注意が必要です。
摘便も同様に、硬くなった便が詰まって出ない場合に行われる方法で、指や器具を用いて便を掻き出します。
なお、便秘解消のためには、病院で行う処置や処方薬の使用だけでなく、生活習慣の見直しが重要です。
便秘解消のために心がけたい生活習慣
前述のとおり、便秘を改善するには生活習慣を整える必要があります。排便のリズムを整えるためには、毎日朝食を摂り、トイレに行く習慣を作りましょう。
腸の動きを促すためには、排便に使う腹筋を鍛えることも大切です。日頃から体を動かす習慣のない方は、適度な運動を取り入れるよう心がけましょう。腹部のマッサージも腸の動きを促すのに役立ちます。
また、ストレスは便秘の一因となるため、リラックスできる方法を見つけてストレスを溜めないようにしましょう。
食物繊維を多く含む食べ物や発酵食品は、便秘解消に効果が期待できるため、意識的に食事に取り入れることが望ましいです。水分不足も便秘の原因となるため、日頃からこまめに水分を摂るよう心がけましょう。
便秘薬にだけ頼らず、生活習慣から見直して便秘を改善しよう
便秘薬にはさまざまな種類があり、便秘の症状によって適切なものを選ぶことが大切です。
なお、症状が重い場合は自己判断を避け、医療機関で相談しましょう。便秘薬の処方だけでなく、症状や原因に応じた適切な治療やアドバイスを受けることができます。
便秘が深刻ではなく、ほかの症状もない場合は、市販の便秘薬を試すのも1つの方法です。酸化マグネシウム便秘薬は、腸ではなく便に作用するため、腹痛やクセになることを心配する方でも服用しやすいでしょう。
なお、健栄製薬の「酸化マグネシウムE便秘薬」はオンラインショップでも購入可能です。病院や薬局に行くのが難しい方は、ぜひご利用を検討してみてください。
もし、便秘薬を試しても症状が改善されなかったり、ほかに気になる症状が出ていたりしたら、早めに医療機関で受診しましょう。
ただし、便秘薬だけに頼らず、生活習慣の見直しもして便秘を改善するよう心がけましょう。