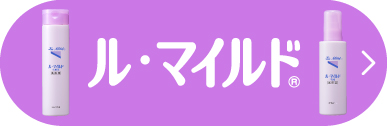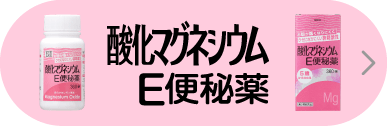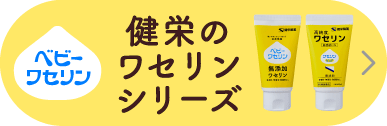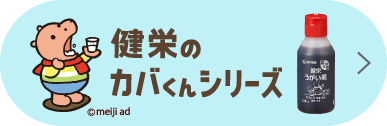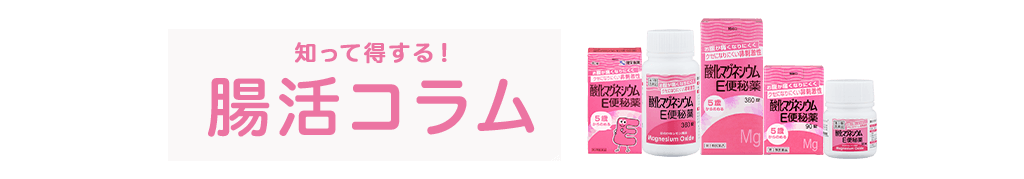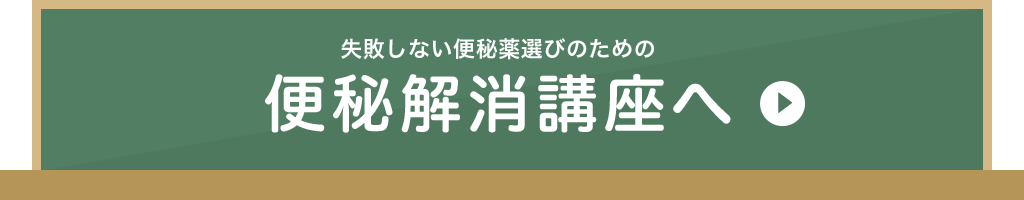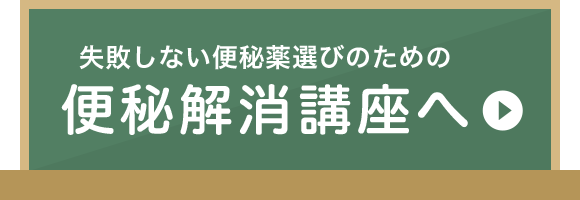VOL.48 腹痛の原因は便秘?セルフチェックの方法と適切な対処法を解説

日頃から排便回数が少なく、腹痛が続いている場合は、便秘が原因である可能性があるでしょう。実際、便秘が原因で腹痛やお腹の張り、吐き気などの不快な症状があらわれることがあります。
今回は、便秘と腹痛の関係や、慢性便秘症の診断基準に基づくセルフチェックの項目、便秘のメカニズム、便秘への対処法などを紹介します。
排便回数が少なく、腹痛に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
便秘は腹痛を引き起こすことがある
便秘が続くと、腸内に溜まった便が腐敗し、硫化水素やアンモニアなどの有害物質が発生します。これらの物質によって腸内にガスが溜まり、腹部の張りや膨満感、腹痛を引き起こすことがあります。
また、腸の動きが乱れ、便がうまく排出されないときにも腹痛が生じやすくなります。とくに、腸が緊張するタイプの便秘では、腹痛を伴うケースが多くみられます。
強い痛みや不快感がある場合には、無理に我慢せず、早めに医療機関を受診しましょう。
便秘による腹痛の特徴
便秘による腹痛は、とくに左下腹部に痛みが出やすく、腸が便を押し出そうとする際に痛みが生じやすいです。
痛みの感じ方はさまざまで、キリキリと刺すような鋭い痛み、鈍く持続する痛み、周期的に差し込むような痛みなどがあります。
また、腸が痙攣(けいれん)を起こしている場合の痛みは、一定の間隔で繰り返されるのが特徴です。
こうした痛みは、排便後に軽くなる場合がほとんどです。症状が続く場合は、ほかの原因が隠れている可能性もあるため、注意が必要です。
便秘で腹痛以外にあらわれる症状とは?
腹痛以外の便秘による症状は、「吐き気」「嘔吐」「下腹部の不快感」「腹部の膨張感」などです。症状がひどくなると、日常生活に支障が出るほどつらく苦しい状態が続くことがあります。
ほかにも、便秘はニキビなどの肌トラブルを引き起こすことがあります。腸内にガスが発生することで背中や腰部を圧迫し、腰痛の症状があらわれることも少なくありません。
さらに、便秘によって自律神経が乱れ、肩こりを誘発することもあります。便秘と肩こりの関係については明確には解明されていないものの、便秘は体のあらゆる部位に影響を及ぼす可能性があります。
慢性便秘症の診断基準に基づくセルフチェック
便秘のつらさには個人差がありますが、日常的に排便トラブルを抱えている方は、「慢性便秘症」の可能性も考えられます。
以下の6項目のうち、2つ以上に当てはまり、それが排便の4回に1回以上の頻度で起きている場合は要注意です。
- ・排便時に強くいきむことが多い
- ・コロコロと硬い便(ウサギのフンのような便)が出ることが多い
- ・排便後もすっきりせず、残っている感じがある(残便感)
- ・排便時につっかえるような感覚がある(排便困難感・閉塞感)
- ・指で肛門を押したり、お腹を押したりして排便を助けることがある
- ・排便回数が週に3回より少ない
これらの症状が6ヶ月以上前から続き、直近3ヶ月間も同じ状態が続いている場合は、「慢性便秘症」と診断される可能性があります。
気になる症状がある方は、セルフチェックをきっかけに、生活習慣の見直しや医療機関への相談を検討してみましょう。
便秘のメカニズムと原因
通常、便は食べ物を消化していく過程で、残ったカスが水分と混ざり合いながら作られます。
腸内に吸収された水分量が十分であれば、水分がきちんと大腸に吸収されながら、便は適度な硬さに変化します。
しかし、水分の摂取量が少ないと必然的に便が硬くなり、体外へ排出されにくくなります。
排便時によく肛門が切れて出血するようであれば、水分が不足しているかもしれません。スムーズに排便させるためにも、普段からしっかり水分を摂ることが大切です。
また、偏った食生活や生活習慣の乱れも便秘の要因と考えられています。ダイエット中や食べ物の好き嫌いがあっても、食物繊維や水分、脂質を適度に摂取するように心がけてください。
なお、どうしてもトイレに行けない環境にあり、普段から便意を抑制する習慣がある方も便秘になりやすいため、注意が必要です。
便秘の分類方法
便秘にはいくつかの分類方法があります。なかでも代表的なのは、「原因に基づいて分類する」「症状の特徴から分類する」という2つの視点です。
| 分類方法 | 着目点 |
|---|---|
| 原因に基づいて分類する方法 | 腸の動きの異常や病気の有無など、「便秘の原因」に注目して分類する (腸の機能低下による便秘と、病気が原因で起こる便秘) |
| 症状の特徴から分類する方法 | 便秘に伴う症状の出方や特徴によって分類する (便が硬くて出にくいタイプや、ガスが溜まってお腹が張るタイプなど) |
便秘を分類して理解することで、自身の状態に合った対処法や治療法を選びやすくなります。
便秘がなかなか改善しないと感じている方は、自身の便秘がどのように分類されるのかを知るところから始めましょう。
原因に基づいた便秘の分類
便秘は、原因によって「一次性便秘」と「二次性便秘」に分けられます。一次性は、大腸や小腸の機能や働きに問題があり発生する便秘で、二次性は、病気や薬などほかの原因によって発生する便秘です。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
一次性便秘症
一次性便秘は、大腸の働きや病気によって起こる便秘です。以下の3タイプに分類されます。
- ・機能性便秘症
- ・便秘型過敏性腸症候群
- ・非狭窄(きょうさく)性器質性便秘症
以下で詳しく解説します。
機能性便秘症
腸の動きや機能が低下しており、便がスムーズに出にくくなるタイプです。腸の形にはとくに異常はありません。
便秘型過敏性腸症候群
便秘に加えてお腹の痛みや張りがある、ガスが溜まりやすいなどの症状があり、下痢を繰り返すこともあります。
機能性便秘と似ていて、どちらにも当てはまるようなケースもあります。
非狭窄(きょうさく)性器質性便秘症
腸に何らかの変化(形や動きの異常)はありますが、便の通り道が狭くなっているわけではないタイプです。
非狭窄(きょうさく)性器質性便秘症は、さらに以下の2つに分けられます。
| 小腸・結腸障害型 | 腸の一部が拡張したり、動きが不規則になったりすることで、便がうまく流れない |
|---|---|
| 直腸・肛門障害型 | 排便のときの閉塞感や筋肉の働きがうまくいかず、スムーズに排便できない |
二次性便秘
二次性便秘症は、病気や薬の副作用など、ほかに原因があって起こる便秘です。以下の3タイプに分類されます。
- ・薬剤性便秘症(オピオイド誘発性便秘症)
- ・症候性便秘症
- ・狭窄(きょうさく)性器質性便秘症
以下で詳しく解説します。
薬剤性便秘症 (オピオイド誘発性便秘症)
薬剤性便秘症とは、一部の薬が腸の動きを弱め、便が出にくくなる便秘です。
オピオイド鎮痛薬の服用によって起こる「オピオイド誘発性便秘症」以外にも、抗コリン薬や三環系抗うつ薬、抗精神病薬などの作用によって、薬剤性便秘症が起こる場合があります。
症候性便秘症
甲状腺の病気、糖尿病、パーキンソン病など、別の病気が関係している便秘です。
狭窄(きょうさく)性器質性便秘症
大腸がんなどの腫瘍や腸管炎症によって、腸の通り道が物理的に狭くなっているタイプの便秘です。血便や体重減少などの症状があるときは、医療機関を受診しましょう。
症状の特徴による分類方法
便秘は、出る回数が少ないのか、出しにくいのかという症状の特徴からも分類されます。以下で詳しく解説します。
排便回数減少型
「何日も便が出ない」「トイレに行く回数が少ない」といった、排便の頻度そのものが少ないタイプです。
便が出ても硬くてコロコロした状態が多く、便が腸の中に長く留まることで水分が吸収され、さらに便が硬くなってしまうという悪循環が起こります。
排便困難型
便が腸の出口まできているのに、スムーズに出せないタイプの便秘です。
「便が出そうで出ない」「トイレに長くこもる」「いきんでも出ない」「出たあとも残っている感じがする」など、便を出しづらいことが主な特徴です。
原因としては、骨盤底筋のうまく使えなさ(排便のコントロール障害)や、直腸の感覚低下、便意を我慢するなどがあります。
とくに高齢者や女性に多く見られ、毎回の排便に時間がかかる傾向にあります。
腹痛を伴う便秘の改善方法

便秘による腹痛は、排便することで症状が緩和する可能性があります。不快感から解放されるためにも、日頃から排便を促すケアを行いましょう。
便秘に伴う腹痛の改善方法は主に以下のとおりです。
- ・運動をして排便を促す
- ・物繊維や善玉菌が含まれている食べ物を摂取する
- ・市販の便秘薬で排便を促す
上記の改善方法のうち、できることから試してみてください。
運動をして排便を促す
運動不足も便秘の原因となるため、日頃から適度な運動習慣を身につけましょう。
とくに、腹筋を鍛えることが大切です。便を排出する際に、肛門に力を入れる必要があるため、腹筋を鍛えて便を押し出す力をつけましょう。
また、腹筋の力が弱まると腸のぜん動運動も低下しやすくなります。筋肉トレーニングやウォーキング、ランニング、水泳などの有酸素運動を生活に取り入れてみると良いでしょう。
運動により便意が促されることもあるため、負荷の少ない運動から始めてみてください。
食物繊維や善玉菌が含まれている食べ物を摂取する
便秘解消には食物繊維が多く含まれた食材を摂取することが推奨されています。食物繊維は便量を増やし、排便リズムを整える効果が期待できます。
緑黄色野菜や、ごぼう・たけのこ・サツマイモ・大豆・ふき・切り干し大根・七分搗き米は、食物繊維を多く含む食材ため、おすすめです。
また、ヨーグルトなどの善玉菌が含まれている食べ物は腸内環境を整え、排便を促してくれる効果があるので、毎日の食事にプラスしてみてください。
また、冷水や冷牛乳も排便を促すことがあるので、便秘でお悩みの方は試してみると良いでしょう。
市販の便秘薬で排便を促す
食生活の見直しや運動習慣を取り入れても便秘の症状が改善されない場合は、酸化マグネシウムを使った便秘薬で腸の動きをサポートする方法もあります。
酸化マグネシウムは腸に水分を集めて便をやわらかくするため、お腹にやさしく自然な排便を促すのが特徴です。
なお、健栄製薬の酸化マグネシウム便秘薬は、公式オンラインショップでも購入可能です。便秘による腹痛や不快感をやわらげたいときの一時的なケアとして、取り入れてみるのも良いでしょう。
ただし、持病のある方、ほかの薬を服用中の方、初めて服用する方は、医師や薬剤師に相談の上、使用してください。
なお、便秘症状が長く続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
便秘による腹痛は放置せず早めに対処しよう
便秘による腹痛は、腸内に便やガスが溜まることで引き起こされる不快な症状です。排便によって解消されるケースが多いですが、生活習慣の乱れや体質によっては慢性化することもあります。
水分補給や食生活の見直し、適度な運動を習慣づけることが、便秘の根本的な改善につながります。それでも改善が見られない場合は、酸化マグネシウム便秘薬を一時的に取り入れる方法も有効です。
ただし、腹痛が強い、長引く、便が出ない状態が続くなど、いつもと違うと感じたときは自己判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。