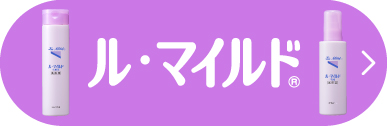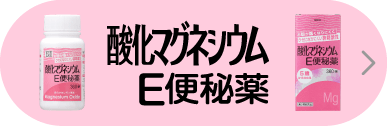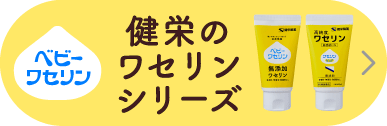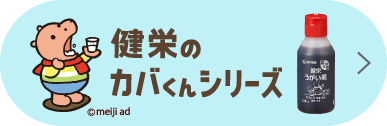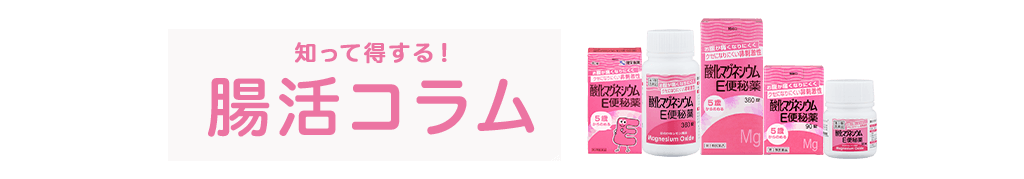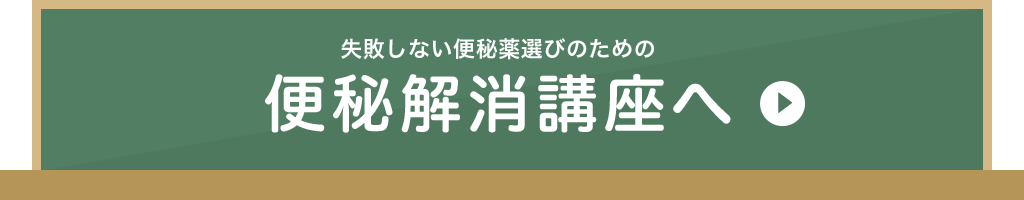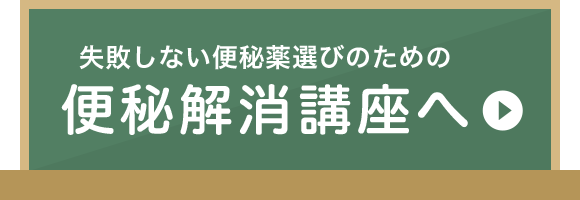VOL.71 牛乳を飲むとお腹が張る原因や対策を解説!つらい便秘の改善方法も紹介

牛乳を飲んだ後にお腹の張りや腹痛、下痢を起こしやすく、牛乳を苦手と感じている方は多いのではないでしょうか。
牛乳を飲んで不調が起きる場合は、体質の問題や腸の疾患、アレルギーなど、複数の原因が考えられます。
今回は、牛乳でお腹が張る原因と対策方法をまとめて解説するため、牛乳で不調を起こしやすい方はぜひ参考にしてください。
また、日常で取り組める便秘の解消方法もあわせて紹介するため、つらい便秘に悩んでいる方もチェックしてみてください。
牛乳を飲んでからお腹が張る原因は?
牛乳を飲むとお腹が張ったり、腹痛や下痢の症状が出たりする方は、まず原因を知ることが大切です。不快な症状を無視して牛乳の摂取を続けると、体に負担がかかる可能性もあるため、無理に飲み続けることは避けましょう。
牛乳を飲むとお腹が張ったり、腹痛になったりするときに考えられる原因は、主に以下の3つです。
- ・乳糖不耐症
- ・過敏性腸症候群
- ・牛乳アレルギー
それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
乳糖不耐症
乳糖不耐症は、牛乳に含まれる乳糖を小腸で適切に消化・吸収できず、腹痛や下痢などを起こす症状です。
小腸で乳糖を分解するための「ラクターゼ」という酵素が少ない、または働きが弱い方の場合、乳糖が分解されずに大腸に運ばれ、ガスや酸を発生させて腹痛や下痢を引き起こします。
乳糖不耐症は、日本人の4〜5人に1人が持っているといわれる症状です。個人差はあるものの、乳糖不耐症の方でも一定量の牛乳を摂取することは可能です。
また、乳糖不耐症の症状が出た場合、乳糖の摂取をやめれば数時間から1日程度で症状がおさまる傾向にあります。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは、小腸や大腸に特別な異常がないにもかかわらず、精神的ストレスなどが原因で腸が敏感になり、便秘や下痢、腹部膨満感といった症状を引き起こす疾患です。
乳糖の少ない牛乳などを飲んでも症状が出る場合は、過敏性腸症候群の可能性が考えられます。
ただし、自己診断は難しいため、気になる症状がある場合は医療機関に相談することが大切です。
牛乳アレルギー
牛乳を飲んだ後に腹痛などの症状が出る方は、牛乳アレルギーの可能性もあります。牛乳アレルギーは、牛乳に含まれるタンパク質が原因で起こる食物アレルギーの1つです。
過敏性腸症候群の場合と同様に、乳糖の少ない牛乳でも症状が出ることがあります。
牛乳アレルギーの場合、腹痛や下痢、お腹の張り以外に、じんましんや呼吸困難、アナフィラキシー反応などの重篤な症状を引き起こすこともあるため、気になる症状がある際は、早めに医療機関を受診しましょう。
牛乳でお腹が張る場合の対策方法
牛乳でお腹が張る場合、以下の対策を行うことで、症状がやわらぐ可能性があります。
- ・乳糖の少ない牛乳やチーズ・ヨーグルトで代替する
- ・牛乳を数回に分けて飲む
- ・牛乳を温めて飲む
それぞれの対策方法について詳しく解説します。
乳糖の少ない牛乳やチーズ・ヨーグルトで代替する
健康のために乳製品を摂取したい方は、乳糖の少ない牛乳やチーズ・ヨーグルトで代替するのがおすすめです。
乳糖を分解して含有量を減らした乳飲料や、加工や発酵の過程で乳糖の量が減少しているチーズ・ヨーグルトであれば、乳糖不耐症の方でも症状が出にくい可能性があります。
牛乳を数回に分けて飲む
牛乳を数回に分けて摂取する方法も取り入れてみるのも良いでしょう。
一度に大量の牛乳を摂取せず、少量に分けて飲むことで、ラクターゼの分泌が少ない方でも乳糖を分解しやすくなり、お腹が張りにくくなる可能性があります。
牛乳を温めて飲む
牛乳を温めて飲むことで、ラクターゼの働きが活発になりやすいほか、腸への刺激も抑えられるため、腹部の不快感を軽減できる可能性があります。
ココアやコーヒー、紅茶と混ぜて摂取するのもおすすめです。
牛乳は体に合えば便秘改善が期待できる飲み物
「便秘解消には牛乳を飲むと良い」と聞いたことがある方も多いでしょう。
牛乳には難消化性の乳糖が含まれており、その一部は消化されずに大腸にたどり着き、腸内細菌を分解して酸が生じるといわれています。発生した酸は、大腸にいる細菌の栄養となり、善玉菌が優位となる腸内環境づくりに役立つと考えられます。
そのため、体質的に牛乳が合う方は、便秘解消法の1つとして牛乳を取り入れてみるのもおすすめです。
ただし、牛乳を飲んで不調を起こしやすい方は、便秘解消が目的であっても、無理な摂取は控えてください。
牛乳以外で便秘を解消する方法

便秘の原因は、ストレスや食生活などさまざまです。牛乳は便秘解消に役立つ食品ですが、便秘を根本的に改善するには、食生活や生活習慣も見直す必要があります。
日常生活で取り入れられる便秘解消法の例は、以下のとおりです。
- ・食物繊維を積極的に摂取する
- ・適度な運動をする
- ・生活のリズムを整える
- ・酸化マグネシウム便秘薬を服用する
それぞれの便秘解消法について詳しく紹介するため、ご自身の生活習慣を振り返りながらご覧ください。
食物繊維を積極的に摂取する
食物繊維は、便秘改善に欠かせない栄養素です。食物繊維には、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があるため、両方をバランス良く摂取しましょう。
不溶性食物繊維は、玄米や大豆などに多く含まれる栄養素で、腸を刺激してぜん動運動を促す作用があります。水溶性食物繊維は、わかめなどの海藻類に多く含まれており、有害成分の排出や善玉菌の増殖をサポートする効果が期待できます。
なお、食物繊維が豊富な食品については、以下もあわせてご覧ください。
「【医師監修】食物繊維が多い食べ物を紹介!摂取量の目安も解説」
適度な運動をする
1日に10~15分程度の運動をするのもおすすめです。運動して体を動かすことで、血行が良くなり、腸の動きも活発になるといわれています。
また、運動不足の方が便秘になるのは、腹筋が弱いことも原因の1つと考えられます。腹筋が衰えていると、排便時にいきむ力が不足するためです。
運動は週末にまとめて行うのではなく、毎日継続することが大切です。便秘が気になる方は、腹筋を中心に、バランス良く筋肉を鍛えましょう。忙しくて運動の時間が取りにくい場合は、すき間時間に腰をゆっくり横にひねるだけでも腸を刺激できます。
生活のリズムを整える
便秘解消を目指すには、生活リズムを整え、排便習慣をつくることが大切です。
毎日決まった時間に起床、就寝、食事をする習慣をつけると、自然と排便のリズムも整います。
とくに、朝食後は腸の運動が活発になりやすいため、毎朝トイレに行く時間を決めて、便意がなくてもトイレに座る習慣をつけると良いでしょう。
また、不眠が便秘の原因になることもあるため、睡眠は十分に取りましょう。早めに布団に入り、リラックスした気持ちで眠ることがポイントです。
酸化マグネシウム便秘薬を服用する
酸化マグネシウム便秘薬は、腸内の水分を集めて便をやわらかくし、排便しやすくする薬剤です。非刺激性で、お腹が痛くなりにくくクセにもなりにくい上、5歳以上の子供から妊婦、高齢者の方まで幅広く服用できます。
酸化マグネシウム便秘薬は、健栄製薬のオンラインショップでも購入できるため、つらい便秘が続く方は、利用を検討してみてください。なお、酸化マグネシウム便秘薬を使用する前には、必ず使用上の注意をよく読みましょう。
また、酸化マグネシウム便秘薬を牛乳やお茶で服用すると、十分に効果が発揮されない場合があります。酸化マグネシウム便秘薬を飲む際は、コップ1杯以上の水またはぬるま湯で服用してください。
加えて、酸化マグネシウム便秘薬の服用中に大量の牛乳を摂取すると、ミルクアルカリ症候群を引き起こす可能性もあります。服用中に牛乳を飲む際は、500ミリリットル以内を目安に、飲み過ぎに注意しましょう。
牛乳を上手に取り入れて便秘解消を目指そう
牛乳は、体質に合えば便秘改善に良い影響を与える飲み物です。牛乳を飲んでもお腹に不調が起きない方は、便秘改善の一環として牛乳を飲むと良いでしょう。
ただし、便秘を根本的に改善するには、牛乳だけに頼るのではなく、生活習慣の見直しも必要です。
それでも便秘が続く方は、酸化マグネシウム便秘薬を服用するのも1つの方法です。お腹の張りが悪化する場合や、ほかの症状が気になる方は医療機関を受診しましょう。